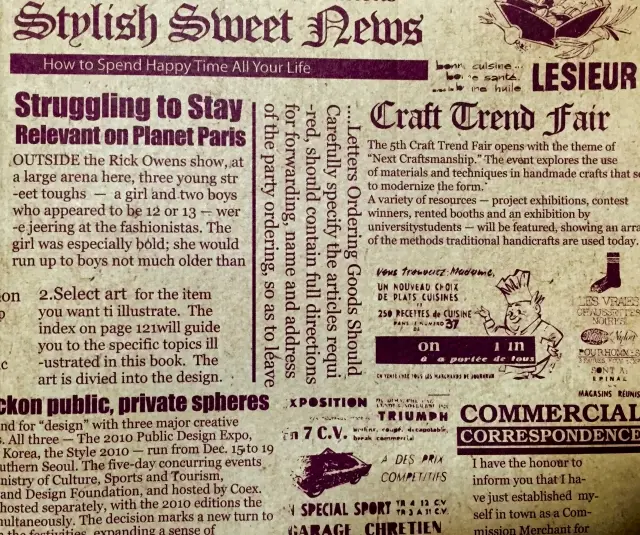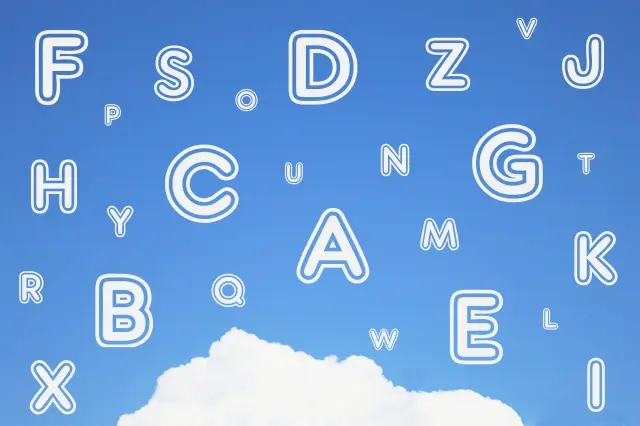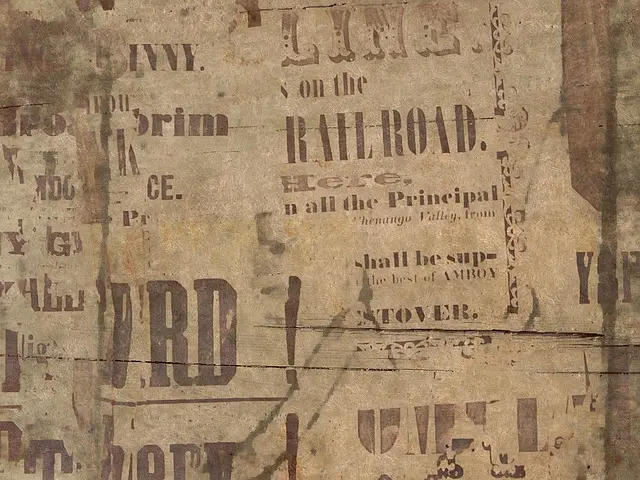選択疑問文とwhichの疑問文との違い
クリップ(1) コメント(2)
8/16 6:16
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
ともくん
高1 埼玉県 一橋大学経済学部(70)志望
高1です。英語で引っかかるものがあったので質問させて頂きます。選択疑問文もwhichの疑問文もorを使って2つのものを提示してどちらかを選ぶという事でした。
例えば
Are you going by air or by train?ーBy train,
飛行機で行きますか、電車で行きますかー電車です。
Which do you like prefer,apples or bananas?ーApples,
リンゴとバナナのどちらが好きですかーリンゴです。
見てわかる通り上の文が選択疑問文で、下の文がwhichの疑問文です。ここで、上の文にはwhichをつけず、下の文にはwhichをつけるのは何故ですか?
上の文によくwhichをつける間違いをしてしまいます。
ネットでもかなり調べたのですが、人によって回答が違っていてどれが正しいのかが分かりません。
個人的には、上の文は自動詞、下の文は他動詞が使われているところが大きな違いなのではないかと予想します。
拙い文章で分かりにくいかと存じますが、回答宜しくお願い致します。
回答
やまじゅんぺー
北海道大学経済学部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
簡単な判別は後の文の要素(SVOC)がかけているか欠けていないか、つまり不完全か完全かで判別できます。Are you going by air or by train?では、You go by air/train.で文の要素が揃っています。しかし後者はYou prefer.で、終わってしまい他動詞なのに目的語が足りていません(like preferは間違えかな?そういう言い回しがあるならごめんね)
Whichはなにかの要素の代わりになるものです、わかりにくいと思うのでもっと詳しく説明すると、whichはこの場合はapplesかbananasの代わりになっています。You prefer which(apples/bananas).ということです、わかるかな?
やまじゅんぺー
北海道大学経済学部
34
ファン
9.4
平均クリップ
4.6
平均評価
プロフィール
北大総合文系入試ひとけた.センター85%(765/900).二次数学87%, 二次国語62%, 二次英語75%. 高三の8月バイト90時間
メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
コメント(2)
ともくん
8/16 6:28
まずlike preferは僕の間違いです。本当にすみません!likeは要りません!
やっと分かりました!ありがとうございます😊
やまじゅんぺー
8/16 6:32
わからんこと他にあったらメッセージで聞いてね〜、英語得意だし復習になるから、乁( • ω・乁)