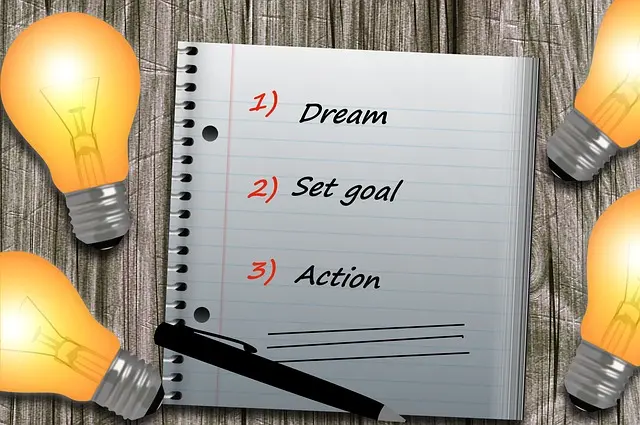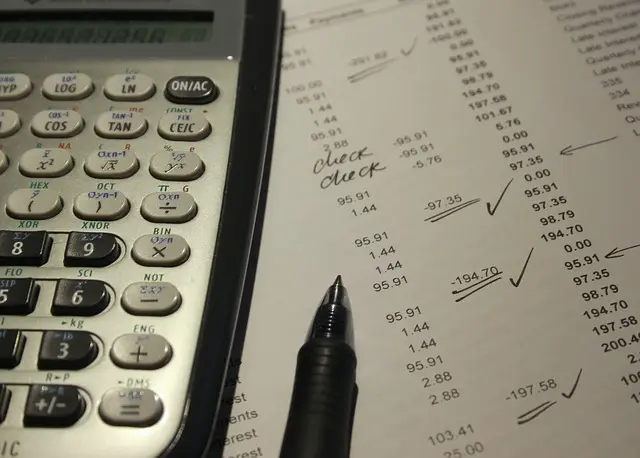基礎固めについて
クリップ(4) コメント(3)
4/3 0:42
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
2004
高2 長崎県 広島大学医学部(56)志望
広島大学医学部保健学科看護学専攻を志望している者です。先日あった合格者体験記で、最低でも5、6月くらいまでには基礎固めをしておいた方がいいと言うのを先輩から伺いました。私は英語と国語が得意で、数学と化学基礎、生物基礎の理科科目が苦手です。
私が受ける学科は、共通テスト(900点満点)と二次(800点満点)の配点比率がほぼ1:1で、二次は国英の2科目で受けるつもりなので、数学はまだしも理科基礎の重要度はそれほど高くないと思うのですが、やはり苦手ということもあるので6月までにある程度できるようにするべきでしょうか、?
(数学も理科基礎と同じくらいまったくできないので、こちらは今からすぐに始めて積み重ねていこうと思っています。)
どなたかご回答よろしくお願いします🙇♀️
ちなみに、進研模試での偏差値は、国語は65、英語は67、数学は48、日本史60、理科基礎はどちらも48くらいという成績です。
回答
あおい
東京大学文科三類
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
数学は1年かけて頑張ってください。英語もキープしてください。そしたら理科基礎は全然後でで間に合います。正直1ヶ月もあれば何とかなりますが、さすがにそれは危険なので、夏休み頃に1回ちゃんとやって、そこからは1週間の暇な時にちょっとやる程度で、共テ直前になったら過去問や対策問題をやって固めるくらいの感覚で問題ないと思います。
あおい
東京大学文科三類
23
ファン
9.2
平均クリップ
4.5
平均評価
プロフィール
東大推薦 ・受験科目(センター) 国語(現代文、古文、漢文)、数学(2Bまで)、英語、社会(世界史、地理)、理科基礎(生物・物理基礎) ・受験科目(私立) 数学、国語、英語 得意科目:文系数学
メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
コメント(3)
2004
4/3 1:38
回答ありがとうございます!
日本史と倫政は、いつ頃から始めた方がいい等ありますでしょうか、?🙇♀️
あおい
4/3 1:47
私は地理、世界史選択だったので、明言はできませんが、日本史は特にある程度押さえておいたほうがいいと思います。歴史はやはり時代の流れが大切なので、詳しい年号や人物は最悪後ででもいいとして、流れは把握しておくべきです。倫理はちょっと分かりませんが、理科基礎よりは重いと思うのでさすがに1ヶ月前の詰め込み!とかはきついと思います
2004
4/5 2:36
そうですよね!参考にさせて貰おうと思います!本当にありがとうございました🙇♀️