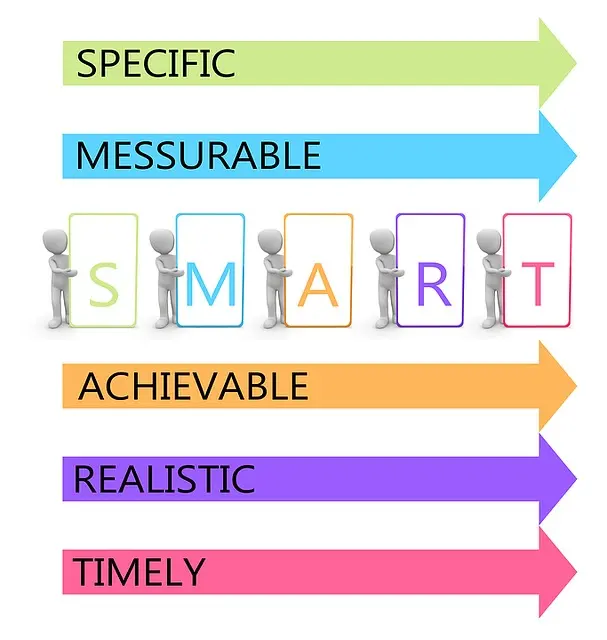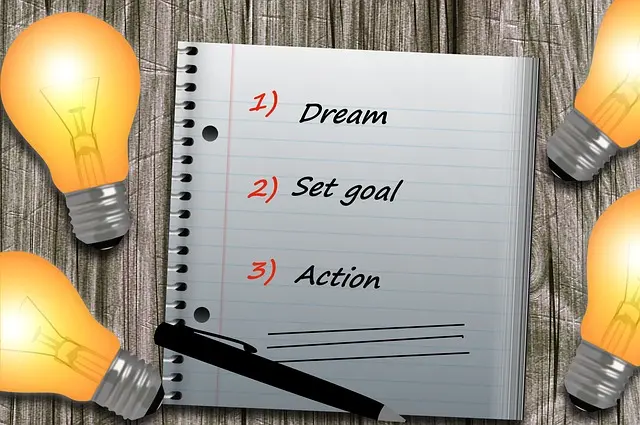テスト前日にやっておくべきこと
クリップ(11) コメント(0)
6/2 23:51
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
snz
高2 高知県 高知大学教育学部(49)志望
テスト前日は「勉強を夜遅くまでやるべき」や「早く寝て次の日にやるべき」とか色々ありますが、おすすめの方法を教えてください
回答
ま
大阪大学基礎工学部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
結論から言うと、早めに寝ることをオススメします。
夜遅くまでの勉強というのはオススメしません。なぜなら、夜は制限時間がない(「朝までまだ◯時間もある」という思考に陥る)ため、効率が落ちます。朝起きて集中して勉強する方がいいでしょう。
また、いわゆる「一夜漬け」というのはあまり効果がありません。たしかに、一夜漬けでテストを乗り切れる場合もありますが、あくまで短期記憶なのですぐに忘れてしまいます。そのため、今後のことを考えるとあまり良くないと思います。
それに、夜遅くまで起きていると、睡眠時間が足りず、テスト当日のコンディションが下がります。6〜7時間は寝ましょう。
欲を言えば、早め早めから対策して、前日の夜は軽く見直す程度で早めに寝るのが一番いいと思います(精神的にも肉体的にも)。
高校の定期テストは大変ですが、頑張ってください!
ま
大阪大学基礎工学部
14
ファン
18.9
平均クリップ
4.6
平均評価
プロフィール
大阪大学基礎工学部一回生 得意科目:物理、化学 塾なしで阪大に現役合格しました。
メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
コメント(0)
コメントで回答者に感謝を伝えましょう!相談者以外も投稿できます。