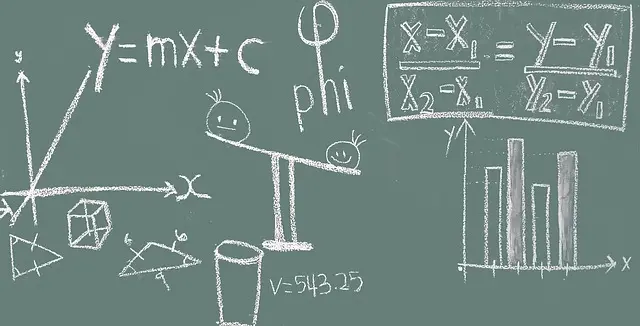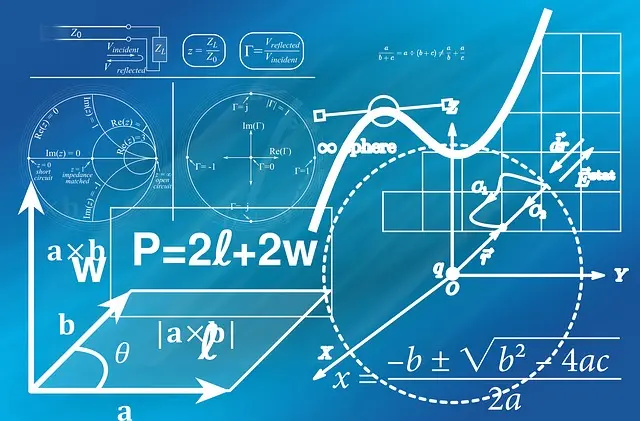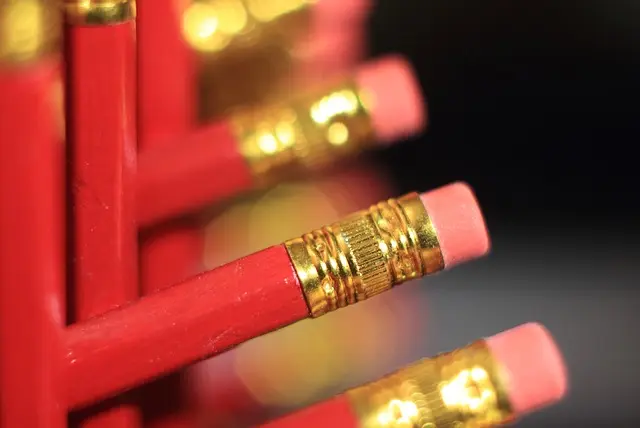阪大合格に向けて(偏差値50くらいから難関大に入学できた人に出来ればお聞きしたいです)
クリップ(30) コメント(1)
8/5 23:53
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
amin
高1 長野県 大阪大学外国語学部(61)志望
私は高一で、偏差値は今50くらいです。
ですが、大阪大学に対してものすごく憧れがあります。諦めるつもりは今のところありません。
ですが、阪大に入る人達は高校偏差値70代くらいの人が多く、周りは気にするなと言い聞かせているのですがやはり無理なのではないかと不安にあります。このまま放っておくと勉強に支障が出てしまうと思い相談させて頂きました。
また、高一でこのレベルまでいってれば合格できそうというラインはどのくらいなのかも知りたいので、教えていただけると幸いです。長文読んでいただきありがとうございました。
回答
むらなん
北海道大学総合教育部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
こんにちは。北海道大学に通っているものです。
阪大の外国語と北大のレベルが同じくらいなので回答させて頂きました。かなり長文になります。
私自身高校偏差値は62、高一の定期テストは必死に頑張って320人中30~45位くらいをさまよっているレベルです。模試になると悪ければ50位60位になることもありました。
その時の偏差値は詳しく覚えていないのですが、進研模試の国数英で120点程だったと記憶しております。
私が北大に入って感じた体感としては、偏差値70だいの進学校の人が4割、偏差値65~69の人が4割、それ以下が2割。高校偏差値50台の人はいなくは無いですが、かなりレアな存在です。
以上のように私の当時の成績と実際受かっている人の高校偏差値について触れてきましたが、次は「今偏差値50で合格できるか」という点に関してです。これに関しては本当に心配いりません。私自身高一の頃は当時の偏差値や判定を意識していましたが、受験勉強を始めていない現段階の偏差値というものの信憑性は大変希薄で、本当にあてになりません。僕の経験では北大に比べ偏差値ではかなり劣る滋賀大教育学部で余裕のE判定もとっています。このような人は私の友達にも山のようにいますし、おそらく全国的にもそうです。
次は「高一でどのレベルまでいっていれば合格できるか」という点に言及していきます。
むらなん
北海道大学総合教育部
6
ファン
13.8
平均クリップ
5
平均評価
プロフィール
北大 総合文系1年です!(現役) 【併願校】同志社 商、経済 立命 経営(共テ利用) 地方出身で高校の偏差値は62と高くないので、その視点からの等身大のアドバイスです。 2次の科目は英語、日本史、国語で、英語と日本史が得意科目です🌱 受験のアドバイスをするのは好きなので、どなたでも気軽に相談してください👍
メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
コメント(1)
amin
8/6 15:28
本当に丁寧に(しかも長文)アドバイスくださり、本当にありがとうございます!是非参考にさせて頂きます!!