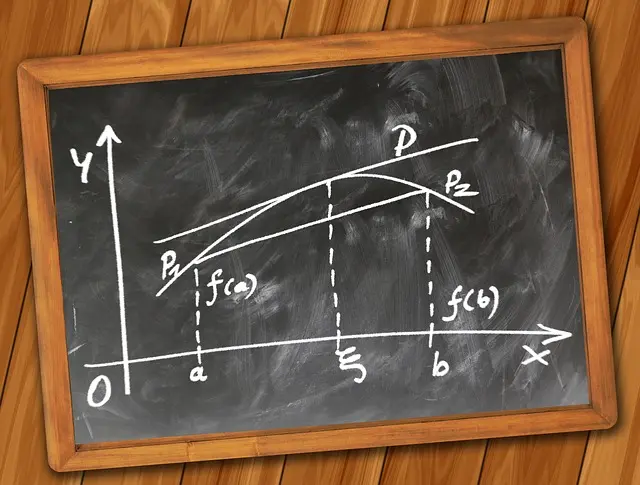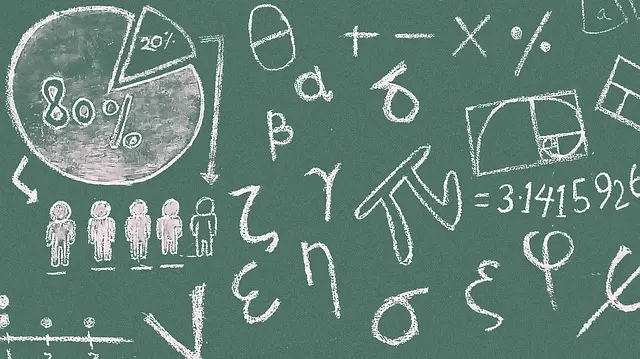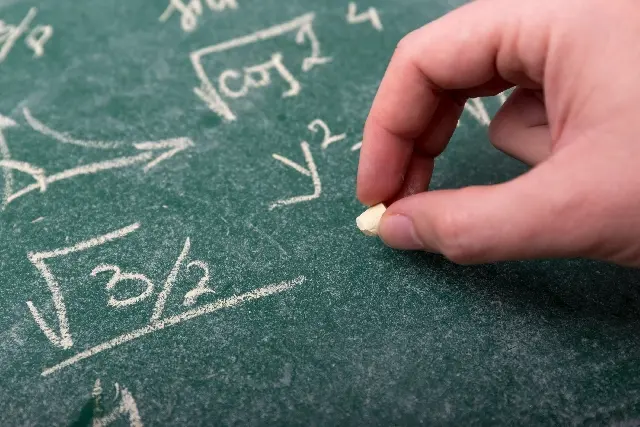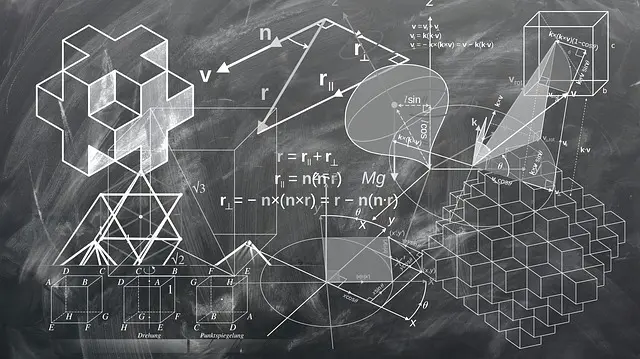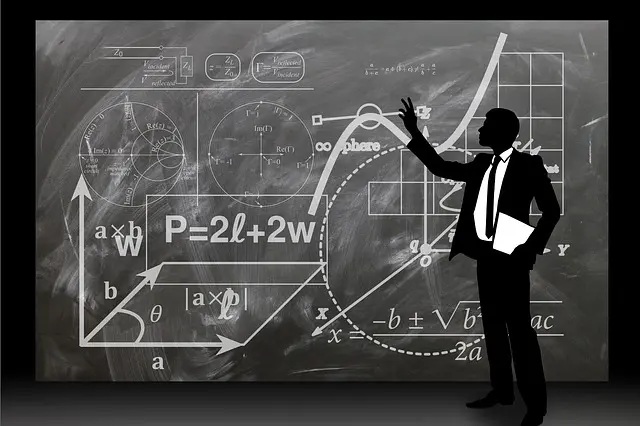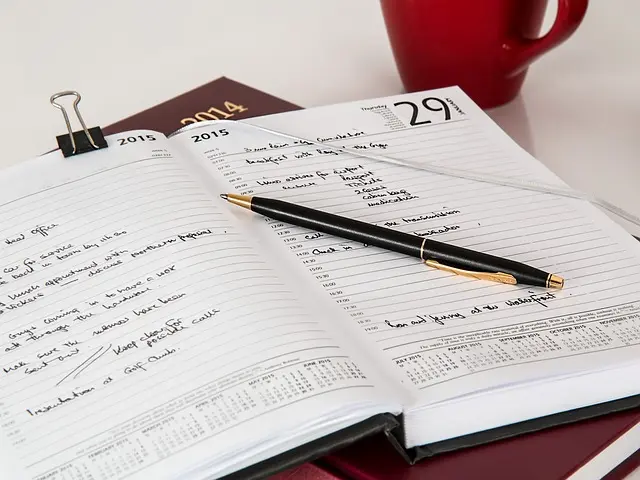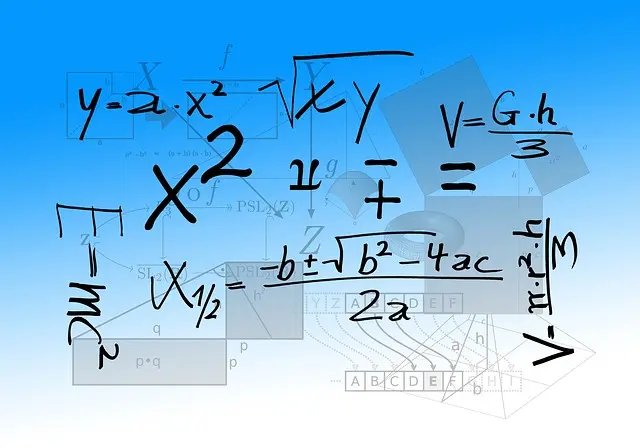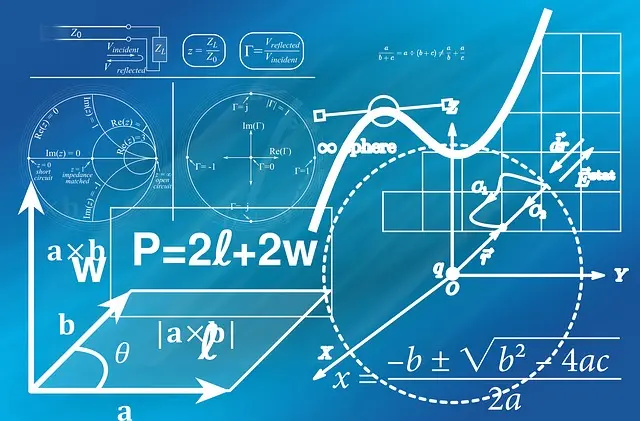阪大理系数学の勉強
クリップ(26) コメント(2)
9/25 22:58
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
Umio.mp3
高卒 大阪府 大阪大学工学部(61)志望
現在基礎問題精巧が完成したので次に核心の標準編を持っているからやろうと思っています。問題数もちょうどよくレイアウトも個人的に好きなのですが、これを終わらせたら後に阪大の過去問またはせか阪をするのはキツイですか??
標準編のみでキツそうであれば難関編を買おうと思っています。
それと実戦模試も解くべきですか?赤本と実戦模試過去問の使用目的や活用方法を教えて頂ければありがたいです。
それと復習でオススメのやり方があれば参考にしたいです。
数学の勉強は量より質だと思っているので自分的にはいいのかなって思ってますが、先輩たちのアドバイスをもらいたいです。
回答
atom
大阪大学工学部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
結論、これから進めるべき順序は以下の通りです。
①核心の星1、2(3は得意でない限り多分しんどい)
②阪大過去問2年以上(特に頻出分野は入念に)
③本番のOP・実践とその復習
④阪大過去問10年分くらいを2周
入試問題の核心の問題チョイスはかなりいいですし、一冊で数Ⅲまで網羅できるのでオススメですが、解答の思考の流れに違和感を持つことがあったので、注意してください。(解答通りの解法でなくて良い。数学センスのある人に質問できると良し)
星3はかなり難しい(正直解けなくても構わない)ので、まず星1、2あたりから始めることをオススメします。
難関編を解いたことはありませんが、正直必要ないと思います。
あくまで、全単元の復習&初見力向上&パターン化が目的という認識で大丈夫です。
入試問題の核心に入る時期もかなり遅めなので、実践模試の過去問は、まず必要ないと思います。
ただ、試験に使った5時間が無駄になるので、本番のOP実戦の復習はしてください。
過去問も同様ですが、復習する際は、どういう力が足りないのか、過去に学んだ知識がどう使われているのかをきちんと分析してください。
普段の勉強の復習法は、
①自力で解く
②解答チラ見
③もう少し自力で解く
④解答を見て、初見の段階でどう考えていれば正解できていたのか考える
atom
大阪大学工学部
104
ファン
16.9
平均クリップ
4.6
平均評価
プロフィール
勉強以外でも幅広く相談・質問受け付けます。1週間以内には返信します。
メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
コメント(2)
Umio.mp3
9/25 23:17
詳細なアドバイスありがとうございます。
勉強を始める時期が遅く残り少ない時間精一杯頑張ります。
それと復習法の抽象化についてですが、具体的にどのようにしてすればいいでしょうか。
過去問の復習方法についても教えて頂ければありがたいです。
atom
9/26 0:14
「抽象化」に関しては、このアプリ内でも色んな人が言っているので、検索して納得するまで読んでみてください。
ざっくり言うと、「こういう時はこうする」とか「こういう時はこれに気をつける」というようにパターン化する感じです。
例を挙げると
・二次式の最小値は平方完成
・両辺を2乗する前に、それぞれ≧0であることを確認(または場合分け)
・楕円は極形式で考える
・複素数を平面上で考える場合、基本極形式に直す
・まずどの分野で構成されているかを意識
・分数の前にマイナスがあるとき、符号に注意
・行き詰まったら、落ち着いて情報を精査
みたいな感じです。
こういう表現だと、「本番でも使える知識」に抽象化出来ていると分かるはずです。
過去問の復習も普段と同様でOKです。
あとは、大学側の意図や傾向、現在の能力とのギャップを意識するようにしてください。
問題の質が非常に高く、一問から学べることが多いので、いつもより丁寧に分析し、時間をおいて解き直しすることも重要です。
ちなみに阪大が受験を通して聞きたいのは
「大学で必要な知識がきちんと身に付いているか」ということです。
(背景として、元々阪大は少し単位が取りにくく、最低限の知識が抜けていると困るため)
①数Ⅲ(微積分、極限、複素数)
②言われた方針通りキチンとできるか(阪大理系学生は真面目なソルジャー気質なので、おそらく自由な発想より誘導に沿って解けるかを最近重視し始めた。高い問題解決能力も求めているので、数学の問題は難解)
③基本的な論文レベルの英語がきちんと読み書きできるか(ある程度の読解スピード、少し難解な読解、英語にしやすい日本語の選択、少し難解な英作をうまく書く能力)
④力学・気体・電磁気(波もたまに出るが、高校レベルの知識は正直あまり役に立たないので、気体の方が頻出)
⑤化学は理論・無機・有機は満遍なく全て必要
全体的に入学以降の実用性重視で、高校止まりの知識は少ないイメージです。