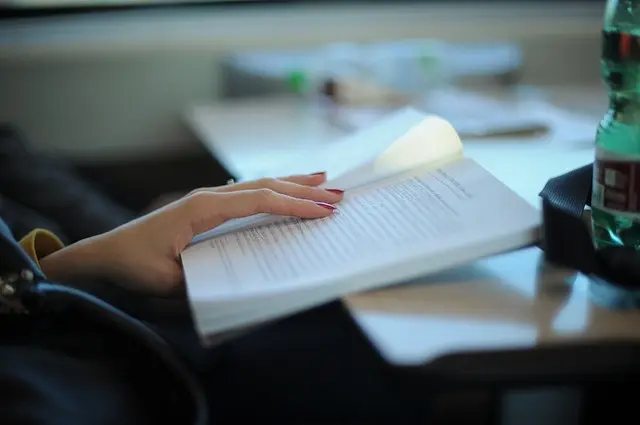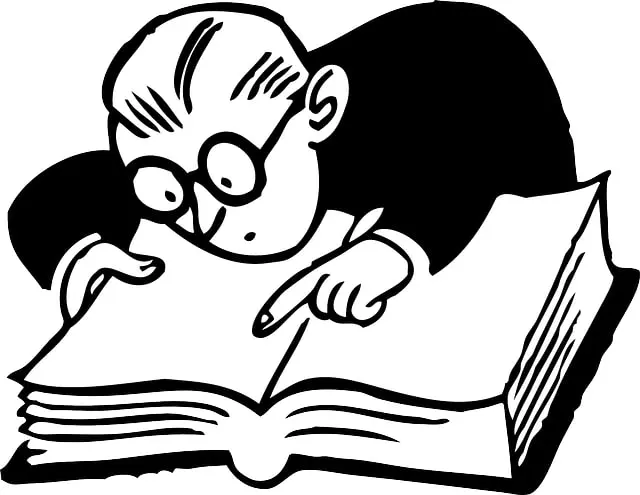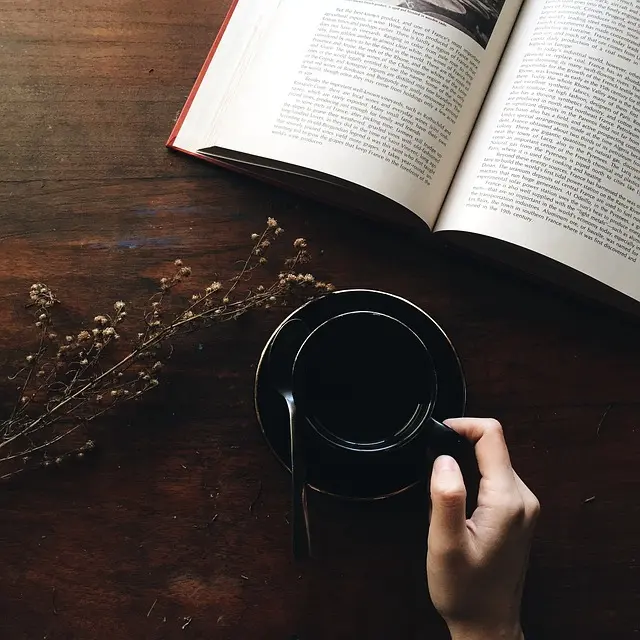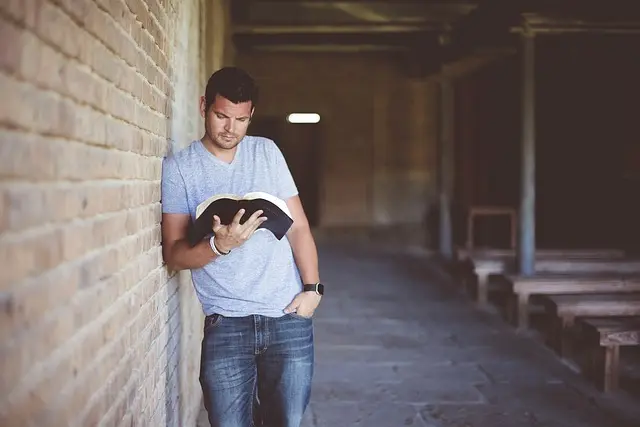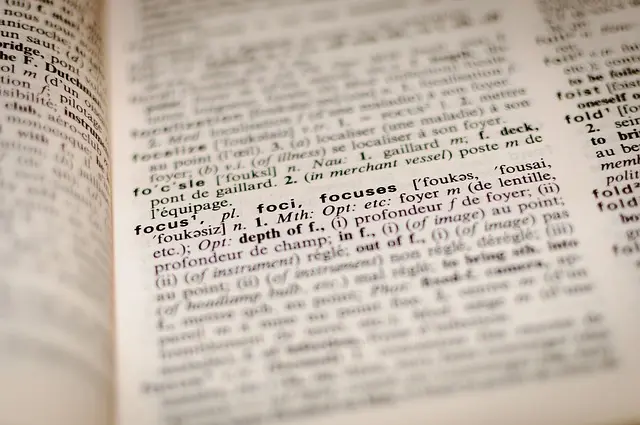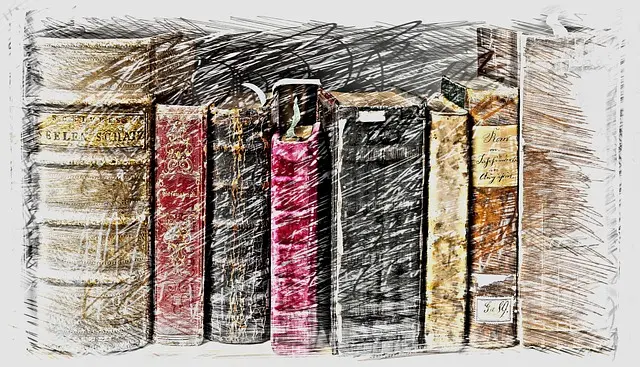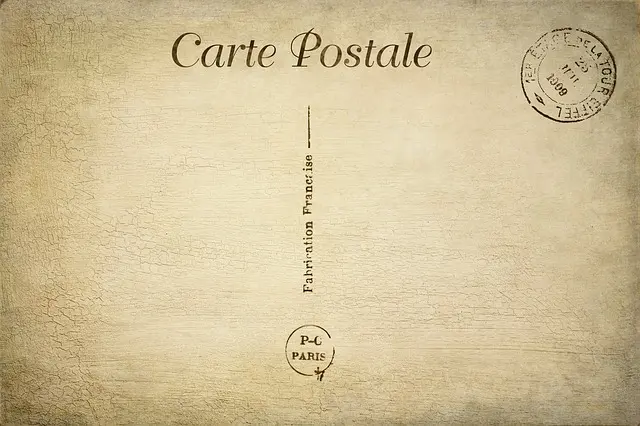「次の文章を読んで、後の問いに答えよ。」について
クリップ(3) コメント(0)
4/22 12:26
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
ああああ
高1 北海道 東京大学理学部(68)志望
『ゼロから覚醒はじめよう現代文』で現代文の勉強をしています。
この本の11ページに「次の文章を読んで、後の問いに答えよ。」というリード文について「これは『文章』に書いてあることをそのまま『答えよ』という指示です。」「絶対に『文章に書いてあるとおりに』答える。」と書かれていますが、これが理解できません。
リード文に対するこの解釈を正しいと仮定すると、「次の文章を読んで、後の問いに答えよ。」としか言われておらず、書いてあることをそのまま答えるべきかは指示されていないので、書いてあることをそのまま答えられておらず、自己矛盾しているように感じます。
よって、単に文章を読んでから後の問いに(自由に)答えよ、という指示であると解釈するのが妥当と考えられますが、これでは、現代文の採点が不可能になります。
リード文をどう解釈するのが正しいのでしょうか?
回答
やかやかさん
早稲田大学商学部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
文章に書いてある通りに答えてください。一切の主観を廃して、自分をAIだと思って回答してください。
自由な記述が許されては、芸術センスを問う試験になってしまいます。
やかやかさん
早稲田大学商学部
162
ファン
7.5
平均クリップ
4.5
平均評価
プロフィール
早稲田商学部現役合格。得意科目は英語と世界史でした。 塾講師の経験をもとに、具体的かつ現実的な提案を心がけます。 基本的にリアリストです。
メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
コメント(0)
コメントで回答者に感謝を伝えましょう!相談者以外も投稿できます。