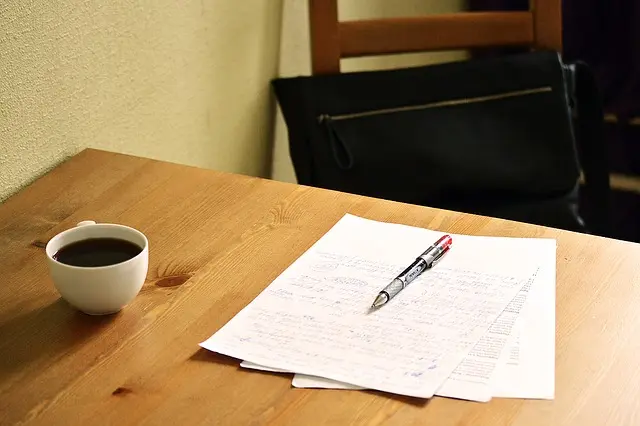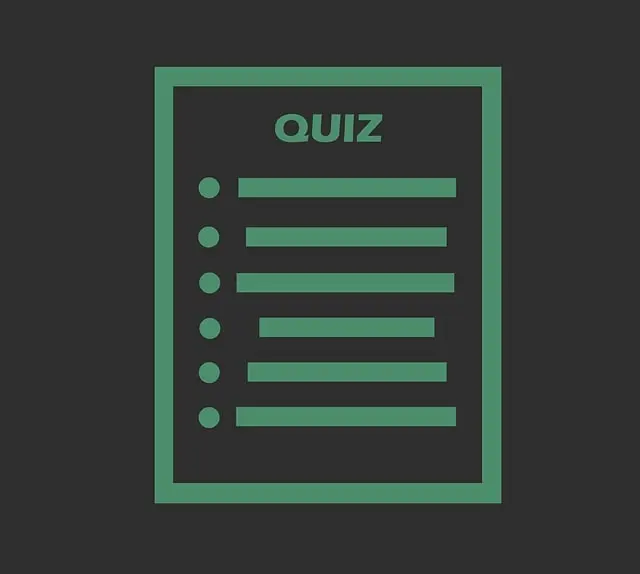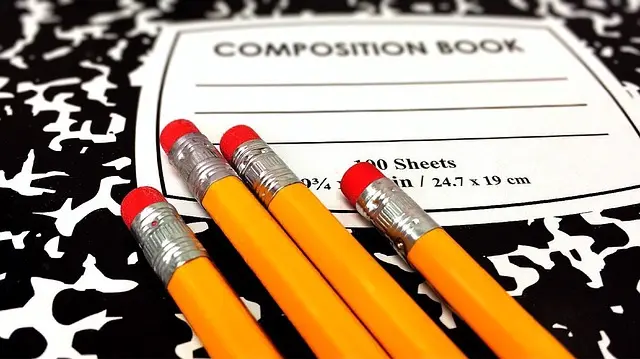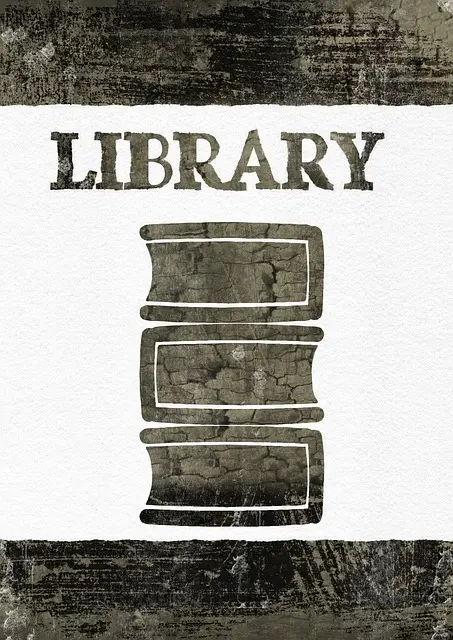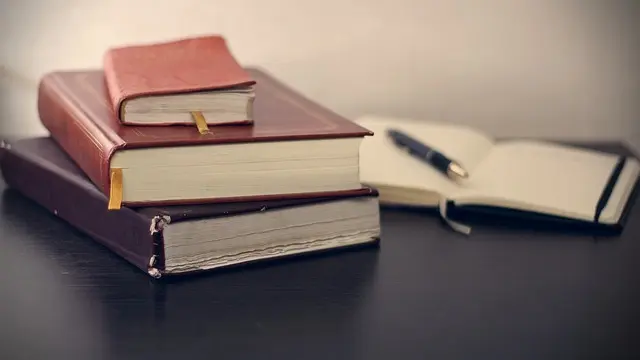テスト直しのやり方
クリップ(25) コメント(1)
9/1 23:40
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
gene
高1 宮城県 東北大学工学部(60)志望
現在、高校一年生の者です。最近はテストが多くなってきてテスト直しがおろそかになってきています。
そこで、どのようなテスト直しの方法を取ればいいか教えてください。
回答
ハジメ
北海道大学水産学部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
テスト直しの方法として主流なものは恐らく、間違った問題を全部解き直す、というものだろうと思います。
しかし (多くの学校で推奨されていますが) 、これは非効率的な方法だと思います。
そこで、テスト直しの方法として、間違えた箇所の記録を提案します。
間違えた箇所の記録は、自分の弱点の把握に直結します。その上、時間の節約になります。
具体的には、テストが返ってきた直後に、間違っていた設問の近くに、その設問の種類を記録するだけで良いでしょう。
設問の種類が不明ならば、教科書や問題集に載っている似ている問題と関連付けるだけでも有意義だと思います。
時間の節約のために、(もしそれが学校が薦める方法だとしても) 既存の勉強法を自分好みにアレンジすることが、これから求められると思います。
P.S
高校一年生の時点で、テスト直しについて注目していること、非常に良いことだと思います。私は正直、受験に先生や学校は不要だと考えています。しかし、自分の弱点を教えてくれる試験は必要だと考えています。テスト直しを軸にした勉強をすれば、安定して点数が取れるようになります。テスト直しなんて、最初は面倒だと思うケド、最初だけだから頑張ってねw
ハジメ
北海道大学水産学部
2
ファン
24
平均クリップ
4.9
平均評価
プロフィール
札幌日本大学高等学校卒 (中高一貫校) 北海道大学水産学部現役合格 高校受験をやったことが無いです。 自分のことは自分が一番把握しているべきだと考えています。 つまり、あなたに一番向いている勉強法はあなた自身が探すべき、と考えています。 ただ、相談には出来るだけ真摯に返すつもりです。 受験勉強の合間の休憩中にでも、ボクのコメントを読んで頂けたら幸いです。 偏差値34も68も経験があります。 中2のときに、スマブラXにはまりすぎて、偏差値34を記録しました。 高2のときに、全国模試の数学で、偏差値68を記録しました。 偏差値なんて所詮数字なので、気にしすぎない方が良いかと思います。
メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
コメント(1)
gene
9/2 23:09
ご丁寧な回答をありがとうございます😊
これからも、自分の目標に向かって頑張りたいと思います。