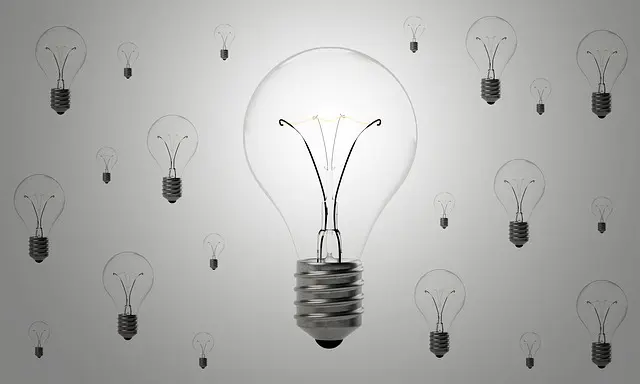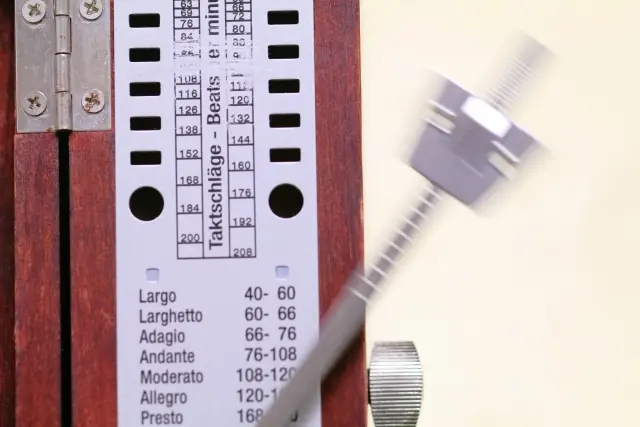物理の運動方程式などを理解するには
クリップ(1) コメント(0)
3/28 10:41
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
なつき
高1 鹿児島県 鹿児島大学志望
物理の高校1年生の範囲がなかなかわからないです。どうしたら頭に入り理解が完璧に出来るのでしょうか。色々なことをして参考にしたいので是非お願いします!
この相談には2件の回答があります
高校の物理を完璧に理解するとなると微積分を用いないといけなくなるので、はじめから全てを理解しようとするのではなく、物理の公式の意味と証明をある程度確認したら、問題演習を通して理解を深めていくのが良いと思います。
九州大学工学部 気体定数
1
0
回答
気体定数
九州大学工学部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
高校の物理を完璧に理解するとなると微積分を用いないといけなくなるので、はじめから全てを理解しようとするのではなく、物理の公式の意味と証明をある程度確認したら、問題演習を通して理解を深めていくのが良いと思います。
気体定数
九州大学工学部
3
ファン
9.2
平均クリップ
4.1
平均評価
プロフィール
福岡県内の私立高校の特進から九州大学工学部電気情報工学科に合格。センター試験804/900。塾に一切通わず、学校と参考書、それからスタディサプリやN予備校、受験系YouTuberなどのネットコンテンツで勉強しました。高校では、理系なのに日本史を選んでしまい成績が伸び悩んだので、倫理・政経を独学することにしましたが、なんとか社会センター9割を達成できました。科目選び、独学の方法などの質問には積極的に答えていきたいと思います。また、アカデミックオタクなので全国の大学の設備・研究力についても多少詳しいです。
メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
コメント(0)
コメントで回答者に感謝を伝えましょう!相談者以外も投稿できます。