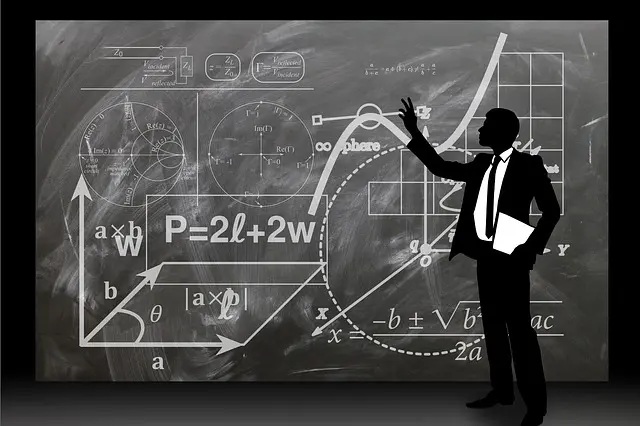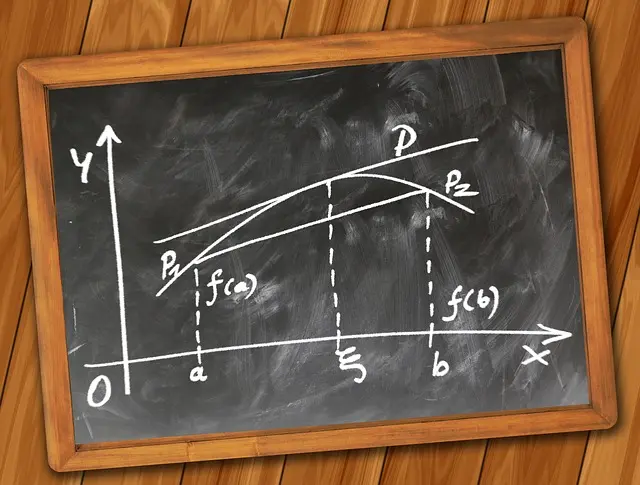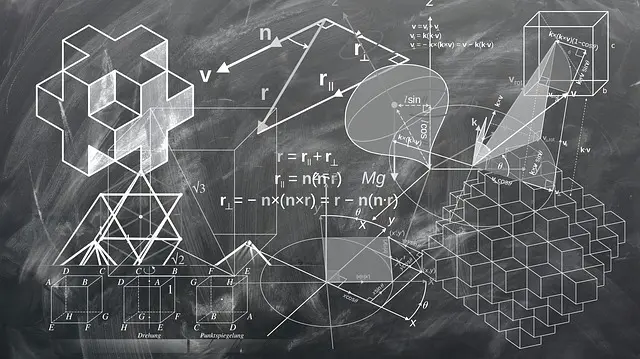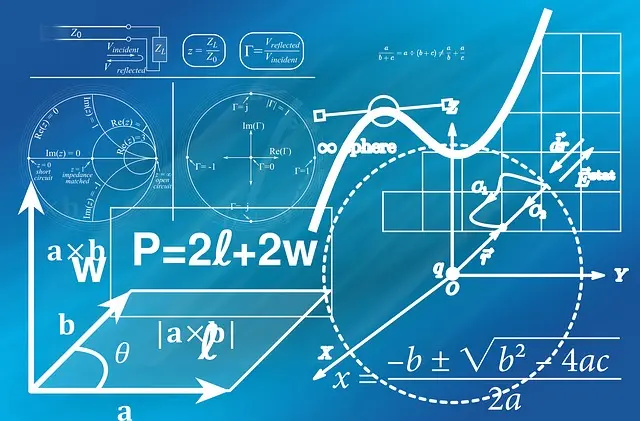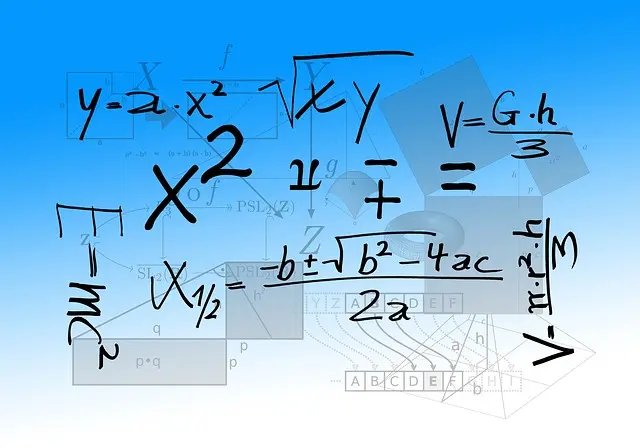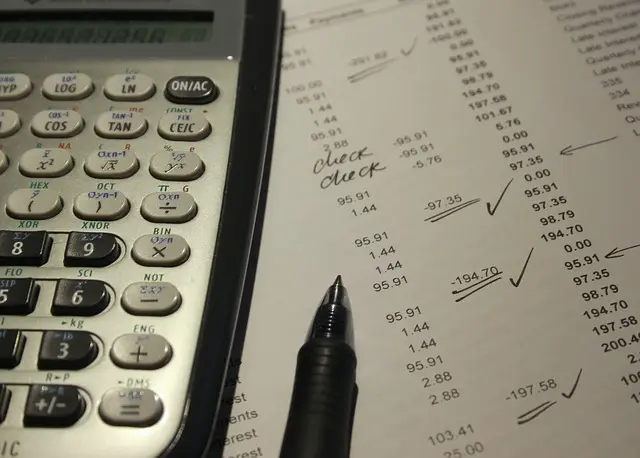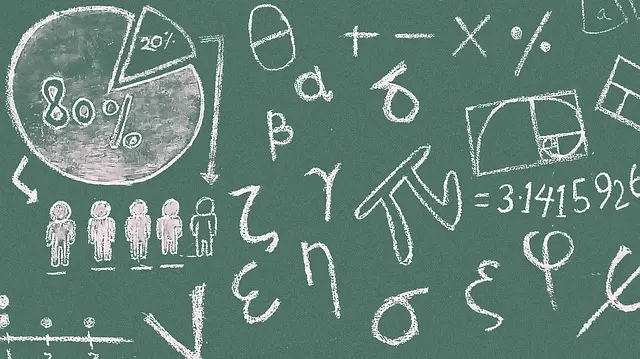黄チャートの勉強法
クリップ(28) コメント(0)
7/11 23:52
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
オレンジポテト
高3 静岡県 愛知学院大学志望
黄チャートを使って勉強しようと思っているのですが、いまいち使い方がわかりません。オススメのやり方を教えていただけますか??
回答
tatsuya1013
早稲田大学創造理工学部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
こんにちは😃
チャート式は問題数がかなり多いので使い方に悩む人が多いですよね(T ^ T)
そこで、数学が得意な人は章末問題から解いて、苦手な部分だけ戻って練習問題を解くと効率よく勉強できると思います(^-^)
一方で数学が苦手な人は章末問題までやらなくていいです!!
その分、1つ1つの練習問題をしっかりと理解することが大事だと思います😁
あとは、自分の志望校に受かるために数学ではどれくらいの点数が必要なのかを逆算して、その分量に合わせてチャートを解くことをオススメします( ^ω^ )
くれぐれもチャートをやりすぎて他の科目がおろそかになるようなことだけは注意しましょう!!
tatsuya1013
早稲田大学創造理工学部
183
ファン
12.5
平均クリップ
4.6
平均評価
プロフィール
早稲田大学創造理工学部総合機械学科に所属する3年生です(^^) 自分が受験生だった頃部活が3年の6月まであったため勉強との両立に苦労しました…… 少しでも受験生の力になれるように皆さんの質問に答えて行きたいと思っています( ^ω^ ) ps:ファンやいいねが増えるとよりたくさんの質問に答えたくなるので気軽にファン登録やいいねをお願いします笑
メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
コメント(0)
コメントで回答者に感謝を伝えましょう!相談者以外も投稿できます。