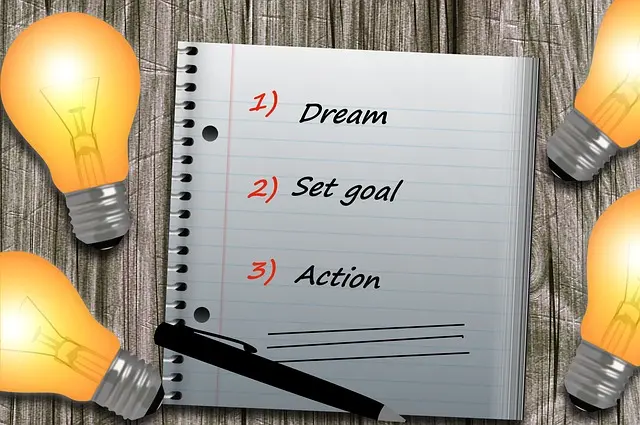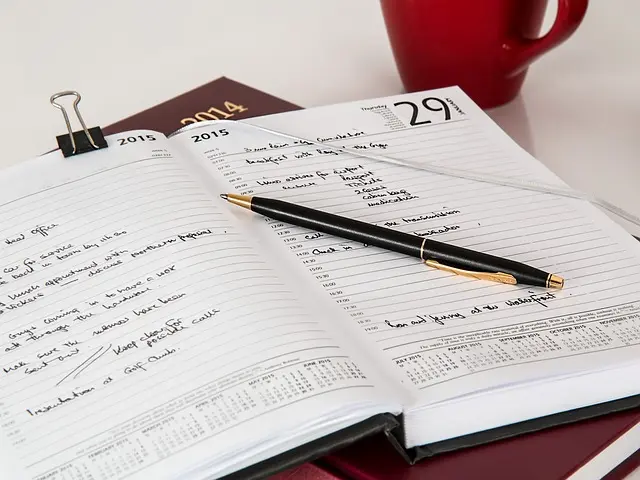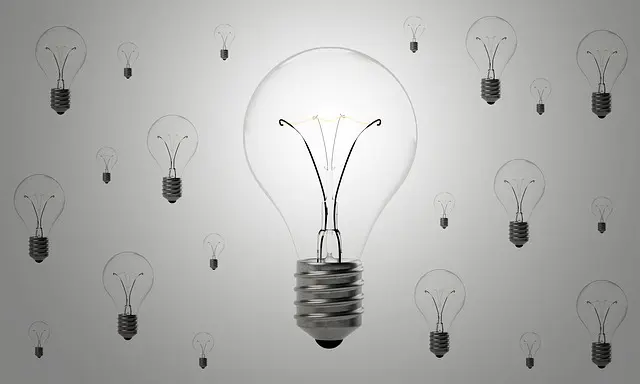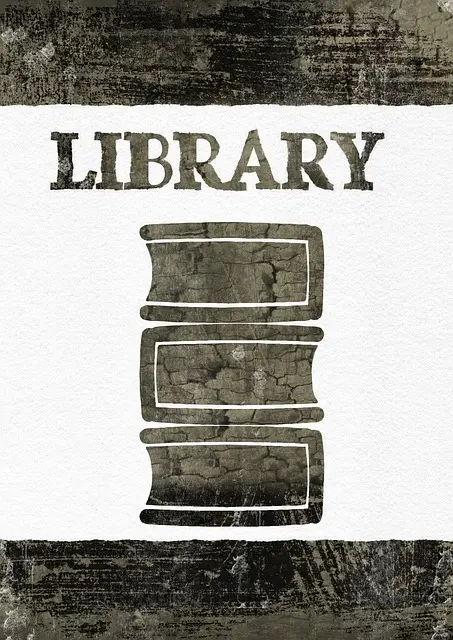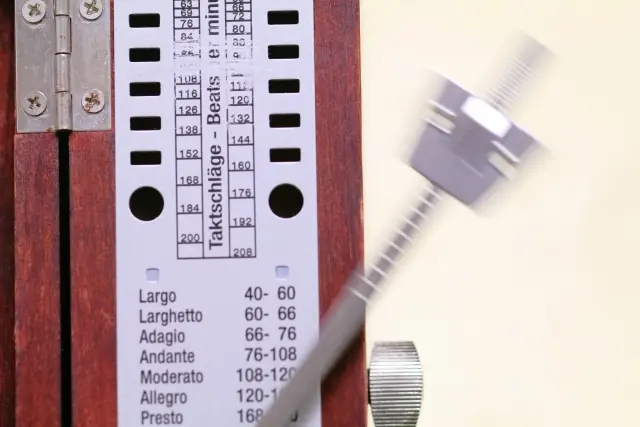理科基礎を始める時期
クリップ(6) コメント(0)
6/8 6:23
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
とみ
高3 東京都 大阪市立大学志望
国公立文系志望です。
塾の先生には早くやった方がいいと言われますが、学校の先生には夏が終わってからでいいと言われています。どうなんでしょうか?
回答
わでぃー
京都大学法学部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
こんにちは、
センター試験で生物基礎と化学基礎を取った僕からお答えさせていただきます!
まず始めに理科基礎の重要度についてです。
どの教科も重要だと思うかもしれません。
しかし、理科基礎は国数英地歴公民に比べて重要度は高くありません。
何故かというと基礎科目2つ合わせて配点が100点だからです。
つまり1つの科目につき50点なのです。
例えば満点が50点の化学基礎と200点の英語ならばどちらに時間をかけた方がいいと思いますか?
文系の2次試験では数学以外の理系科目は使いません。
数学すら使わないところもあります。
それを分かっていれば2次試験で使用する英語や国語に時間を割く方が良いと思いませんか?
また、理科基礎は理系の扱う理科科目と異なり単純なことしか出題されません。
先にも言ったように1科目50点です。
50点の配点の中に教科書の内容を詰めなければならないので、高度な問題を出すことができないのです。
そして理系の理科科目に比べるとそもそも教科書の内容自体が重くないです。
おそらく、理科基礎の問題は問題集を1冊買って一周おわってから過去問に取り組むと満点近い点数を取ることができると思います。
得意不得意にもよりますが、理科科目が苦手でないならば1科目2ヶ月くらいでおおよそ完璧にできると思います。
不得意ならば3ヶ月くらいかかるかもしれません。
旧帝大を目指すレベルの受験生であれば2ヶ月以内に理科基礎をマスターできるようです。
僕は1ヶ月と少し勉強して本番9割とりました。
つまり結論として、夏休み中に始めればかなり十分な時間を取れますし、夏休み後に始めても問題はないと思います。
もし不安であれば今から始めてもいいと思います。
しかし1日1時間程度の勉強にしておいてください。
それ以上の時間は他の教科にかける方が有意義です。
一度解いてみて簡単であれば、わざわざ今からやり続ける必要はないので夏休み明けから始めてください。
何故なら早く取り掛かり過ぎてもどうせ内容を忘れるからです。
それよりも試験に近い時期にやった方が頭に残ります。
それでは応援してます、頑張ってください!
わでぃー
京都大学法学部
215
ファン
34.5
平均クリップ
4.8
平均評価
プロフィール
元まりきゅーという垢でやっていました。 偏差値52の自称進学校から高3まで部活をして塾無し独学で京都大学法学部に現役合格しました。 参考書をあまり使っていなかったので、参考書などよりも受験に対するモチベーション的なことを話す方が好きです笑 毎回長文になってしまうのはごめんなさい! 1つの回答を読んだら他の回答も読んでいいねやクリップしてくれると嬉しいです! 7月はテスト勉強で忙しいので基本的にログインできません!
メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
コメント(0)
コメントで回答者に感謝を伝えましょう!相談者以外も投稿できます。