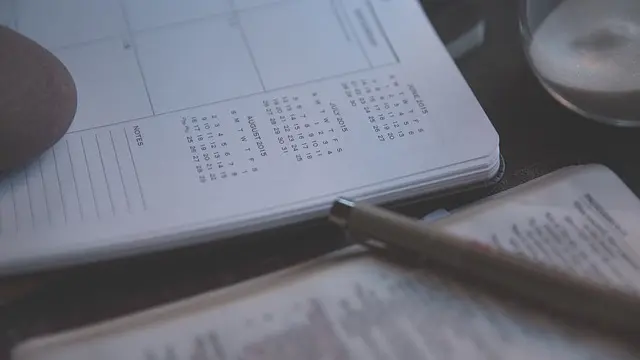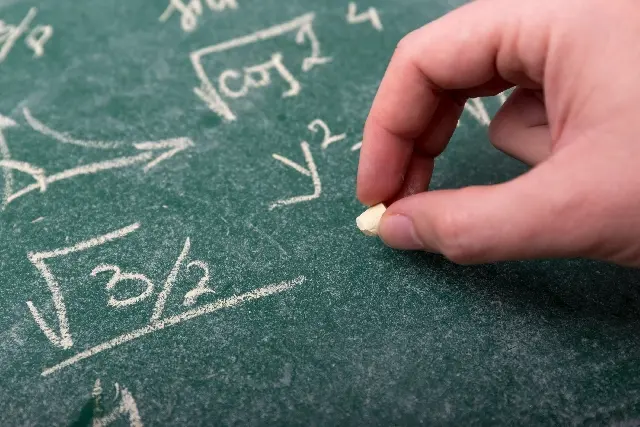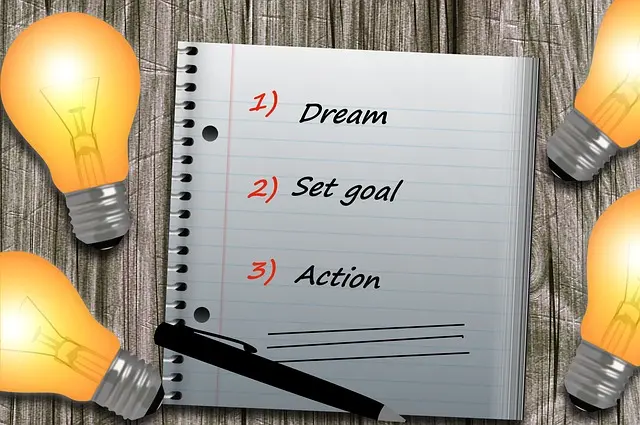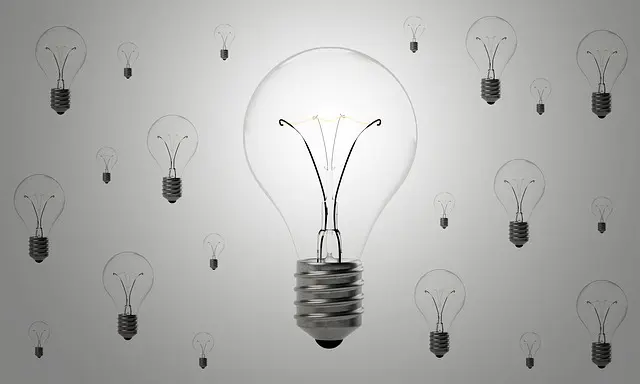物理を先取りする時の勉強法
クリップ(11) コメント(0)
10/7 7:15
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
さみー
高2 神奈川県 東京大学農学部(68)志望
高校2年生で東京大学現役合格を目指しているものです。
公立高校なので、今物理は力学が終わったところです。3年生になつてから理科をやれば良いとよくいわれるが私は、理科が苦手で英語は基礎が固まってきた感じがするので早めに理科に力を入れようかなとお思っています。
出来るだけ早く全範囲終わらせたいと思っていて、10月の中旬から始めて1月までで全範囲終わらせることが理想です。
そこで、独学で3ヶ月くらいで全範囲終わらせらるのかや、おすすめの参考書、どんな感じで勉強していけば良いかアドバイスお願いします。
回答
ゆうき
北海道大学総合教育部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
今は理科に力を入れるよりも数学を完璧にするべきだとは思いますがそれはさておき、三ヶ月で物理を全範囲勉強するなら漆原先生の物理とセミナーを本気でやればいけなくもないです。
漆原先生の本を読み理解
↓
セミナーで該当範囲の問題演習
このサイクルをすれば大丈夫です。セミナー物理は30章くらいあるので、1日から2日で1章、一周終わった段階で慣れてきていると思うので2週目は1日1章で大体完璧になるでしょう。
数学の偏差値が65から70くらいであればある程度基礎力は完成していると思うので上記の勉強をしても良いと思います。
ゆうき
北海道大学総合教育部
37
ファン
4.4
平均クリップ
4.5
平均評価
プロフィール
北海道大学理学部数学科在籍 鬱、不登校の挫折から合格をしましたので、受験勉強とメンタルのバランスの取り方には長けていると思います。 悩み、モチベーションの保ち方等など些細なことでも是非ご質問ください。 また受験生時代は英語と数学が得点源で、特に数学では二次試験の点数をどれだけ粘ってあげるかに重きを置いていたのである程度回答できると思います。 クリップとファン登録、とても励みになります。ぜひよろしくお願いします。
メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
コメント(0)
コメントで回答者に感謝を伝えましょう!相談者以外も投稿できます。