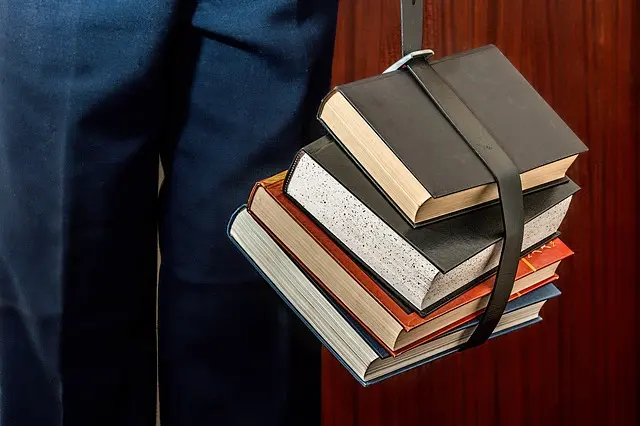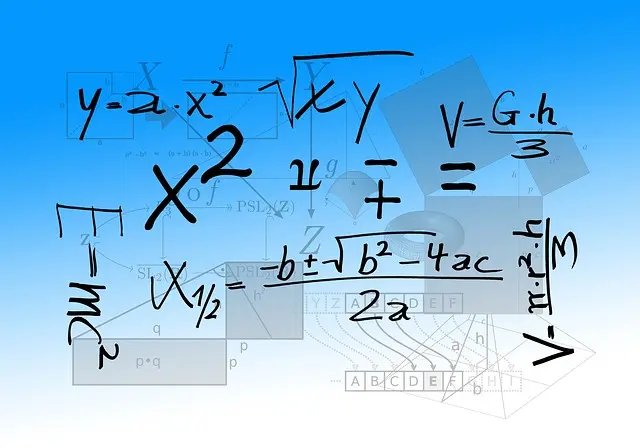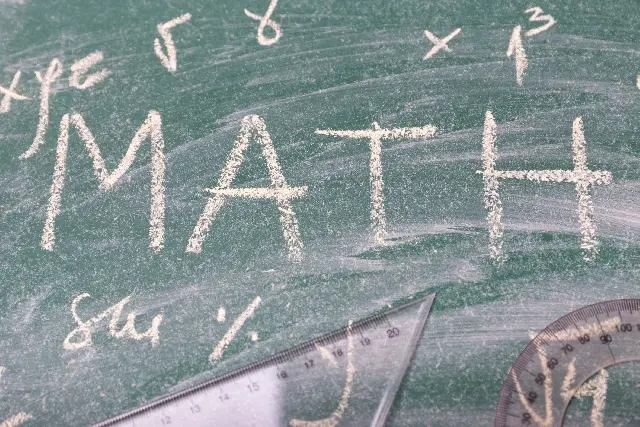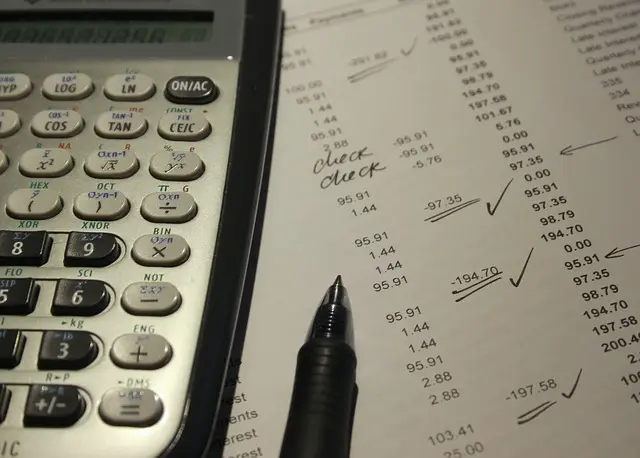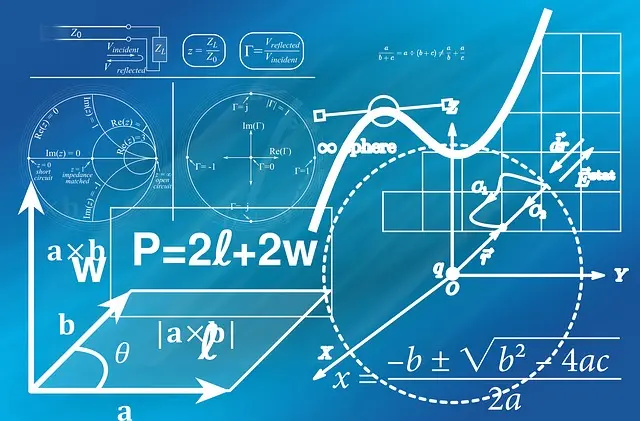数学Bについて
クリップ(2) コメント(1)
9/23 8:49
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
かぶ
高2 東京都 神戸大学経済学部(63)志望
高2神大志望です。
数Bの教科書の最後の章、確率の部分はやった方がいいですか?また、共通テスト数II・Bに出てきますか?
回答よろしくお願いします。(独学です)
回答
riku
九州大学経済学部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
基本はやらなくて大丈夫です。2次試験でも数学を使うとかであれば尚更です。
共通テストは、数学は1・A、2・Bともに5題あるのですが、うち2題が必答問題で、残りの3題は選択問題になります。それぞれ数A、Bの範囲が選択問題になります。つまり、1Aは確率、整数、図形の性質から2つ、2Bは数列、ベクトル、確率統計から2つ選ぶことになります。
ですので数列とベクトルを選択していれば特に困ることはありません。2次試験でも確率統計が出る大学というのはごく1部で、神戸大学ではおそらく出題されないはずです。ですので飛ばしていいでしょう。
なお、共通テストの対策を本格的に始める頃、どうしても数列やベクトルができないとか、数列やベクトルが時間的に合わないとかの時に確率統計を学んで選ぶ人もいます。確率統計は学習すれば他二つに比べてやや解きやすいようです。しかし、基本的にはそのためだけに確率統計をやるのは効率が悪いので、これは例外だと思っておいてください!
参考になれば幸いです!
riku
九州大学経済学部
49
ファン
8.3
平均クリップ
4.8
平均評価
プロフィール
九大の経済学部(理系)に通っています! 現役独学でした!福岡出身です! ぜひクリップ📎お願いします!😊 精神論的なことや抽象的なことは言わず具体的に回答致します!
メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
コメント(1)
かぶ
9/23 9:27
ありがとうございます!