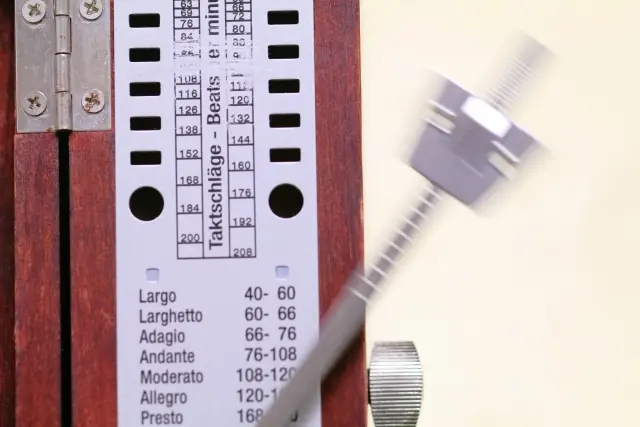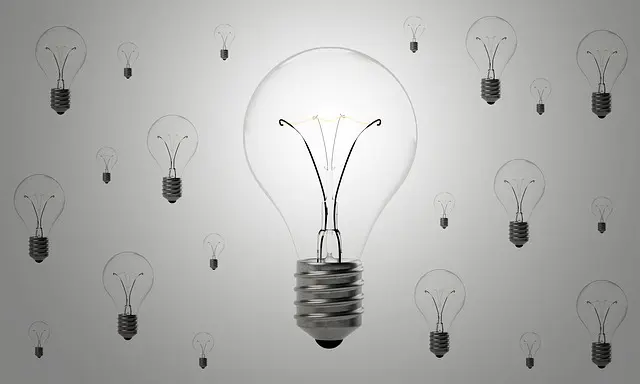物理の勉強方法
クリップ(27) コメント(0)
10/28 13:26
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
青空
高1 北海道 北海道科学大学志望
私立高に通っている高校一年です。
私が志望する大学は工学部なので、
来年は物理を選択しようと考えています。
現在物理基礎を学校で学ばさせて頂いてるのですが、
授業が他の学校とは違く、物理担当教師が予習動画を作って、私達はそれを見てから授業でグループワークを通して問題を解く、という方法でやっています。
ですが私にとってその授業方法は向いていないと感じました。予習がどうしても苦手で、グループワークを通して問題を解くのも苦手なのでやはり家庭で自己学習するしかないと感じました。
物理の点数も悪く、赤点を毎回取ってしまうくらいなので物理を少しでも好きな科目に出来ればいいなと思います。物理のおすすめの勉強方法があればぜひ教えてください。
回答
けろちゃん
名古屋大学工学部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
自分も物理がめちゃくちゃ苦手でしたが、最終的にはセンター物理で100点をとりました。
以下、その勉強法です。
まず本屋で自分のレベルにあった参考書を買ってください。
私はイラスト付きでわかりやすく原理や考え方を教えてくれる、超初心者向けのような本を買いました。
物理が苦手な人は、そもそも嫌いな人も多いので、入口の入りやすやは大事です。
次に参考書を一通り読んだら、問題集の基本問題に挑戦します。
これは学校で購入した問題集とかで大丈夫です。
解けないところは参考書や教科書に立ち返り、原理を理解し難なく解けるようになるまで繰り返します。
それができるようになれば応用問題を解いてください。
また参考書もレベルアップしたものを購入してください。
このレベルの参考書だと、ネットにレビューがたくさんあると思います。
ただ応用まではできなくとも、十分及第点には達すると思います。
頑張ってください!
けろちゃん
名古屋大学工学部
77
ファン
14.4
平均クリップ
4.7
平均評価
プロフィール
就職活動中のため、内定が出るまでお休みします。 コメント、メッセージ等いただいても、返事が遅くなるかと思います。
メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
コメント(0)
コメントで回答者に感謝を伝えましょう!相談者以外も投稿できます。