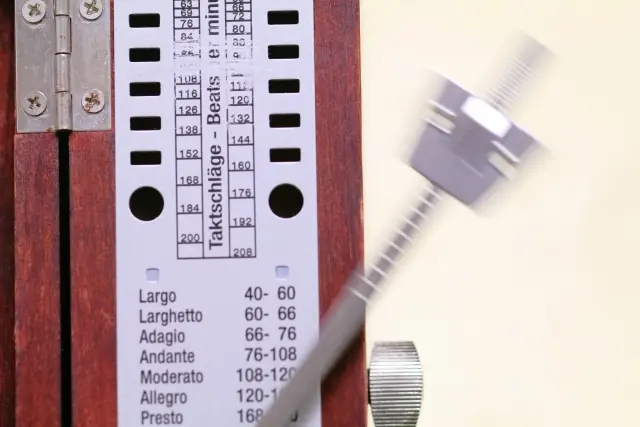物理の勉強の仕方について
クリップ(4) コメント(0)
8/7 22:17
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
りんちゃん
高3 福岡県 福岡工業大学情報工学部(44)志望
物理について学校でセミナーと物理のエッセンスのみ配られたんですけどその2つで物理の効率の良い勉強法などがあれば教えてください!!
回答
コウ
慶應義塾大学理工学部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
物理のセミナーとエッセンスが配布された場合ですが、基本セミナーの内容はエッセンスの内容を包含しているので、最初から物理のセミナーをやるのがおすすめです。基本の内容は教科書から引っ張ってきて、セミナーをすべて解くという流れで行えば進研模試などの偏差値でも軽く70~80まで到達することは十分に可能です。では、エッセンスは活用しないのかという疑問が生まれると思いますが、エッセンスを全部やる意義はそこまでないです。しかし、セミナーにない解法、発想の仕方がところどころに掲載されているため、一読するのはおすすめです。尚、注意したいのは教科書の練習問題から、セミナーの発展問題との難易度の差は割とあるので初学の場合、難しく感じてしまうこともあります。ですが、大学入試で出される問題は、物理の場合典型問題をもとにしているものが多く、普段の演習問題とそこまで難易度の差はないのが特徴です。セミナーに掲載されている問題は、ほとんど網羅的な良問であるので高いレベルに到達したいのであれば、基本的内容を理解した後、その現象のテーマについて語れるぐらい解法を理解し覚えている状態まで達するのが理想的です。まとめますが、物理についての勉強法としておすすめなのはセミナーから手を付ける。(教科書を見ながらでも全然問題ないです。)解法を覚えるぐらいまで演習する。エッセンスは内容を読む程度で苦手分野があったらその分野だけ補強する。この流れで大丈夫です。勉強頑張ってください。
コウ
慶應義塾大学理工学部
2
ファン
88
平均クリップ
4.7
平均評価
プロフィール
現役で慶應義塾大学理工学部を一般受験したものです。東大受験もしましたが、残念ながら不合格になってしまったため、その失敗談も交えながら大学受験を突破するにはどうしたらいいかを真剣に回答します。 科目:数学 物理 化学 英語 国語 地理 前期 東大理科一類 不合格 併願 慶應理工一般 合格 後期 横浜国立大学理工 合格
メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
コメント(0)
コメントで回答者に感謝を伝えましょう!相談者以外も投稿できます。