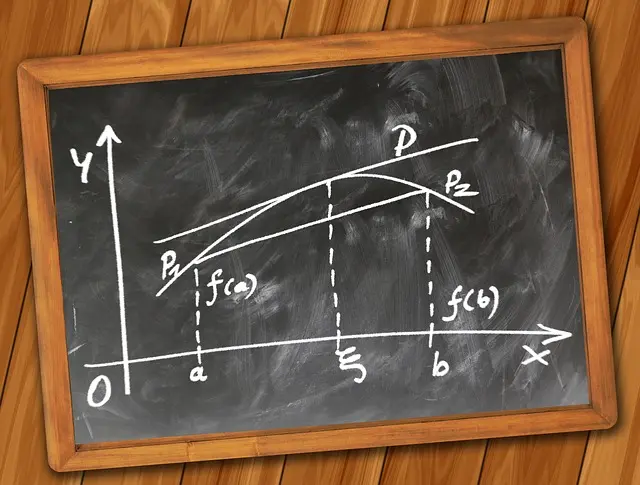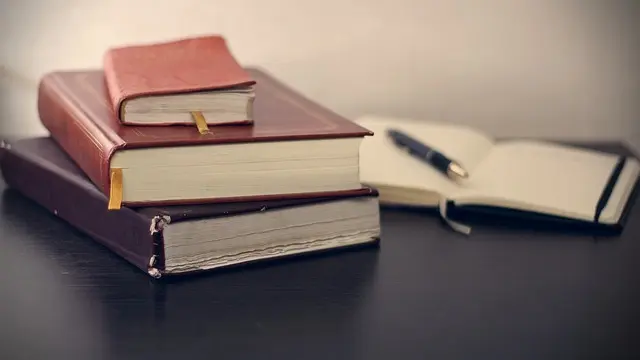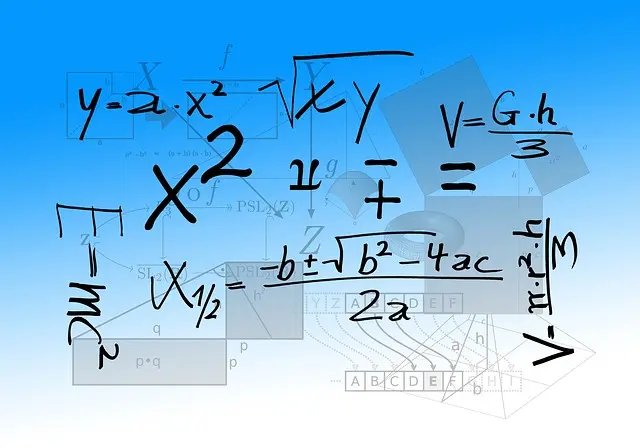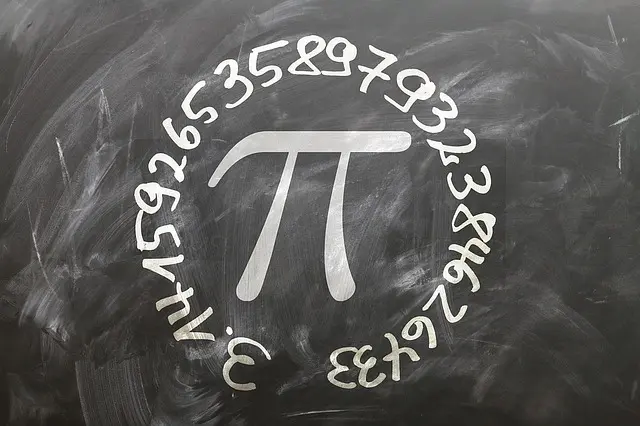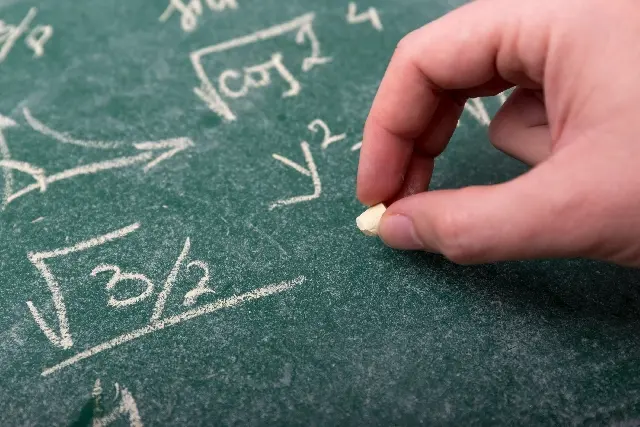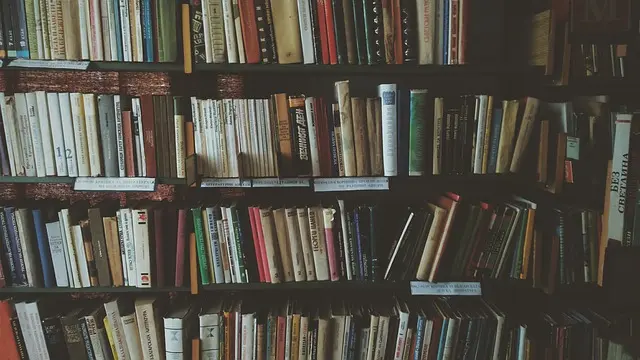数学 記述 どこまで書けばいいのか
クリップ(2) コメント(1)
6/28 21:57
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
ごぼー
高2 北海道 東京大学志望
高2理系の者です。数学ⅡBまで終わったところで、今は青チャートを解いて、解法のインプット、記述に力を入れて勉強しているのですが、進研模試の過去問を解いている時、どこまで詳しく書かなきゃいけないのかな?などと躊躇してしまい、しまいには時間が無くなります。記述でなければ、答えはしっかり制限時間内に導き出せます。そして、模範解答を見ると、ほとんど、自分の迷っていた、これは書くのか?というところが書かれておらず、計算式ばかりでした。自分の詳しすぎるような書き方だと進研模試の狭めの解答欄には収まらない気もします。ただ、駿台模試などは解答欄が大きいので、問題は進研模試よりも難しいですが、しっかりと書けて、なおかつ時間内に間に合います。やはり二次試験に向けて、今からでも正しい記述のやり方は身につけていきたいと思っているのですが、記述において、自分は考えすぎなのでしょうか?これからどのように記述と向き合っていけばいいのか、教えていただきたいです。
回答
Mx
東京大学文科三類
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
東京大学文科三類に所属している者です。
個人的な意見ですが、実際に志望校の過去問を解くようになるまでは少し丁寧過ぎるぐらいに書いた方がいいと思います。説明を削るのは簡単ですが、増やすのは難しいからです。丁寧過ぎることで減点されることはあまりありませんし、もし余計なことを書いて減点されたら今後はそれを書かないようにすればいいと思います。
少しでも参考になれば幸いです🙇♂️
Mx
東京大学文科三類
203
ファン
11.6
平均クリップ
4.6
平均評価
プロフィール
東京大学の4年生です(文科三類→文学部)。 自分は高3の夏の駿台東大模試で総合偏差値42のE判定でした。しかしそこから3ヶ月後の秋の駿台東大模試で総合偏差値を18上げてA判定を獲得、その後現役で東京大学文科三類に合格することができました✨ 【正しい努力】をすれば必ずいい結果に繋がります‼️ 皆さんの努力を【正しい努力】に導くことを心がけて回答やメッセージを送らせてもらっています。少しでも皆さんの勉強の参考になれば幸いです。 よろしくお願いします🙇♂️ 【追記】 社会の選択は日本史と世界史、理科の選択は物理基礎と化学基礎でした。
メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
コメント(1)
ごぼー
6/29 0:57
やはり二次試験を見据えるべきですね!参考になりました!ありがとうございます!!実践してみます!