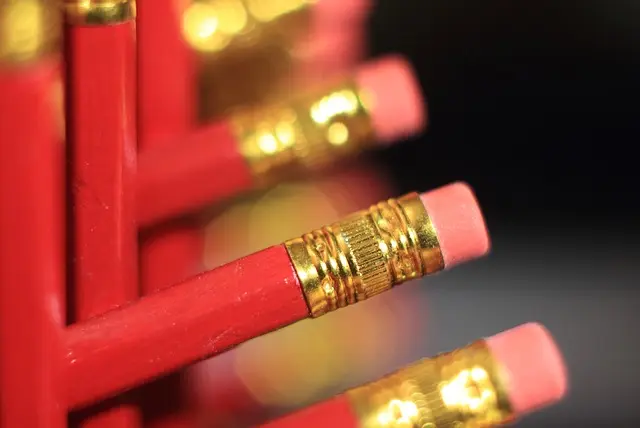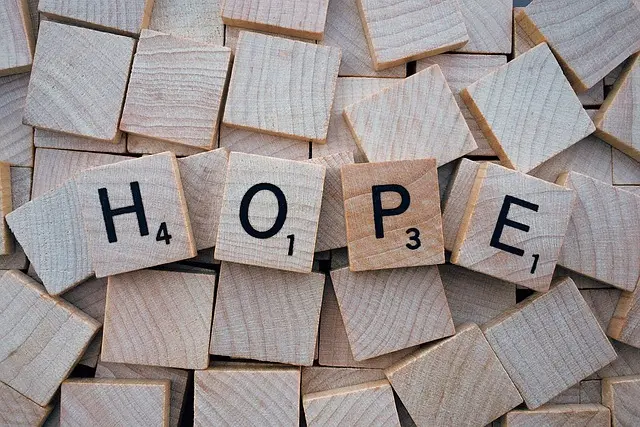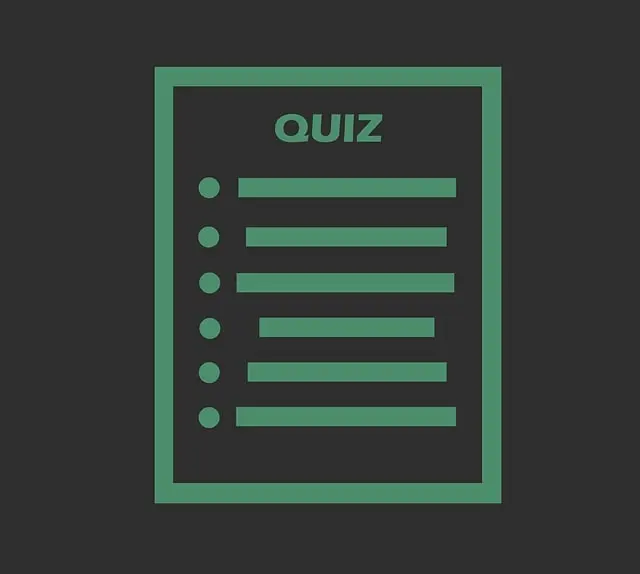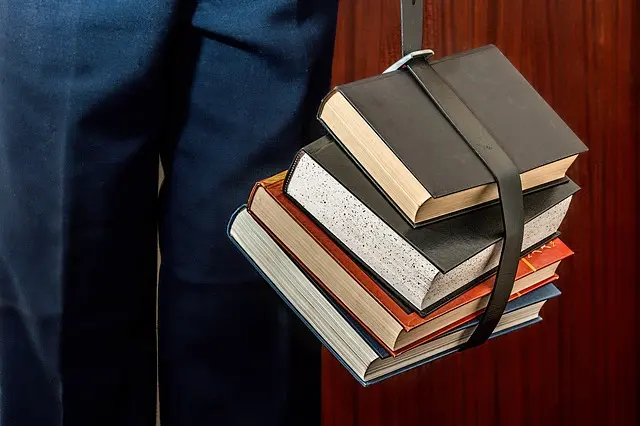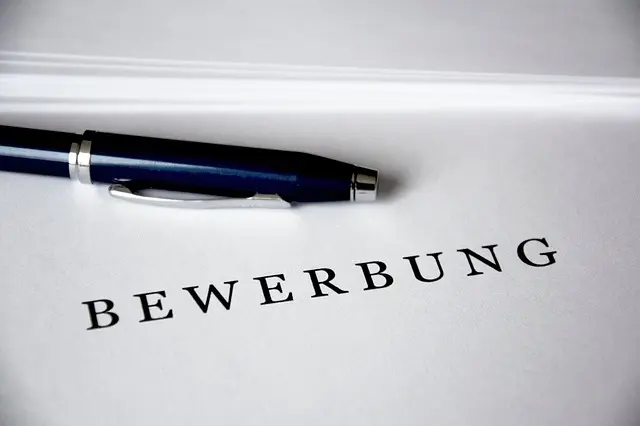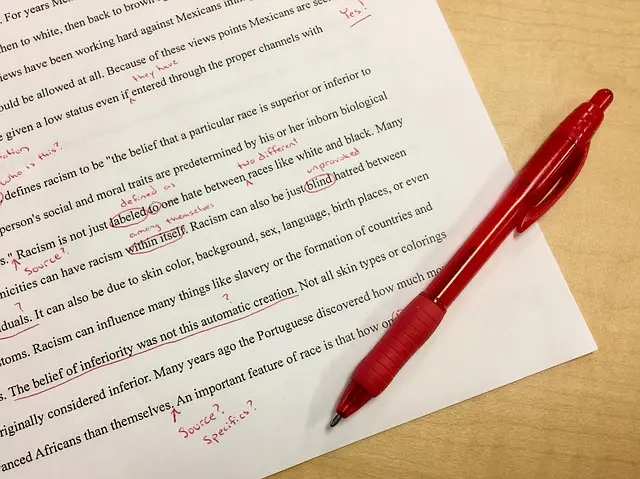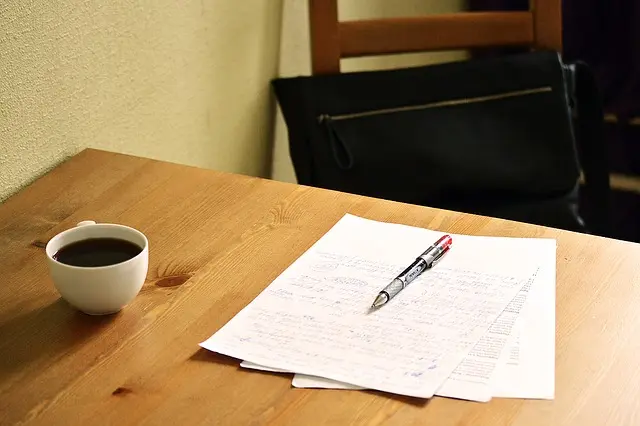英語長文の復習の仕方
クリップ(19) コメント(0)
8/11 12:55
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
優斗
高3 千葉県 北海道大学工学部(60)志望
高3です
自分は高2から英数の勉強は進めていましたがその当時では勉強法というもの確立しておらず
闇雲にやっていたために
問題集や参考書をただこなしただけに終わってしまいました。(今見返しても謎に正解の解答の記憶はあります)
そこで今となって自分の間違え方の癖を把握するために
もう一度手をつけてしまった参考書問題集の間違えの研究(?)
をしても時間の無駄にはなりませんか?(使った問題集のは全てバツ三角を印付けています)
もしくは新しい参考書でのこれから間違えたものを復習した方がいいでしょうか?
回答
たけなわ
北海道大学法学部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
以下は私個人の意見です。
間違いの研究自体は素晴らしいことなのですが、その間違いはなぜ生じたのか、つまりどこで躓いたがために誤答してしまったのかについては、覚えていらっしゃるのでしょうか? 例えば、英文和訳ならここの単語の意味を取れていないとかは過去の自分の答案を見ればある程度はわかると思うのですが、選択肢問題とかになると、自分はどういった根拠をもってこの(間違いの)選択肢を選んだのかということは、自分自身がそれを覚えていない限りは、答案などから推察するのは難しいと思います。その場合は、その問題集から自分の間違いの原因を研究しようとしても、あまり成果は得られないのではないかと思います。何より、解いた問題の見直しによって、自分の間違い方を研究するのは、なるべく早くにやったほうがいいです。模試の見直しも同じですが、自分がどこで躓き、あるいはどこをどう誤解したのかという記憶がなるべく鮮明に残っているうちにやらないと、時間の経過に伴い、その記憶はどんどん失われていきます。そうなれば、もう後の祭です。もう一度解き直すという手も一つですが、正解の解答の記憶があるなら自分の実力が反映されないので、これをやってもあまり意味はないと思います。なので、結局、自分の間違い型の研究は、これから新たにやっていくというのが良いのではないでしょうか。
もっとも、過去にやった問題集も無駄にしたくない場合は、例えば改めて長文を全部和訳してみたり、あるいは、逆に和訳を見て英作文の練習をしたり(その場合は、もとの長文が正しい英訳の一例となります)と、色々工夫の余地はありそうです。
たけなわ
北海道大学法学部
43
ファン
7.8
平均クリップ
4.8
平均評価
プロフィール
気が向いたときに、気が向いたご質問に回答しています。
メッセージとコーチングは、UniLinkで活躍する現役難関大生から個別に受験サポートを受けられる、UniLinkの有料サービスです。どちらも無料体験できるので、「この人についていきたい!」と思える回答者を見つけたらぜひご活用ください。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
メッセージは、全ての回答者にダイレクトメッセージでいつでも直接相談できます。メッセージ数に制限はありません。
コーチングは、希望の回答者があなた専属のオンラインコーチ・家庭教師になります。週に一度のセッションを通して、勉強スケジュールの調整やモチベーションの持続をサポートします。
コメント(0)
コメントで回答者に感謝を伝えましょう!相談者以外も投稿できます。